
山陰の山あいの静かな集落、江津市桜江町(さくらえちょう)。澄んだ水と空気に包まれたこの土地に、今もなお昔ながらの手仕事で紙を漉く工房があります。「石州勝地半紙(せきしゅうかちじばんし)」です。
今回、「つながるいわみ」でお話を伺ったのは、6代目として伝統を守り続ける佐々木誠(ささきまこと)さん。紙に触れた瞬間にも感じる、強さと手作りの温かさ。その一枚一枚に宿るのは、長い歴史を経てこの地で育まれてきた技と想いです。
家業としての紙づくり、幼き頃の記憶にあった原風景
佐々木さんが紙漉きの道へ進まれたのは、30代後半のこと。愛知県立芸大でデザインを学んだ後、東京で会社勤めをされていました。転機となったのは、母方の実家が代々生業としてきた「石州勝地半紙」の存在です。
「江戸時代から紙を漉いていた家系なんです。大人になって、自分がこの仕事に就くことになるとは、あの頃は思いもしなかった。」
江津市に、「風の国」を建設する際に、伝統工芸である石州勝地半紙の工房を作る話があり、それをきっかけに5代目の職人である叔父への弟子入りし、現在の工房で紙漉きの仕事に携わることになりました。
「『和紙=伝統工芸』という堅いイメージがあります。でも、実際に紙を漉いてみると、その奥深さや面白さにどんどん引き込まれていくんです。自分の手で“形になっていく”ものづくりの面白さを改めて感じました」
土から紙まで。すべてが手仕事
石州勝地半紙では、紙の原料である「楮(こうぞ)」を自ら栽培するところから始まります。毎年11月後半ごろから一年分の原料となる楮を刈り取り、蒸して皮を剥ぎ、干す「そどり作業」を12月に7~8回行い、紙を漉く作業は、原料を一晩水に戻し、煮てゴミやキズなどを取り除き、きれいになった原料の叩解作業をし、そして漉いて、干して仕上げるという、すべての工程を手仕事で行っています。
さらに均一な和紙を漉くのに欠かせない粘液『ネリ』の原料「トロロアオイ」も自家栽培しており、まさに「原料栽培から和紙の加工まで」を一貫してを守り続けています。

「この工程を全部やっている工房は、全国でもほんとうに少なくなっていて、手間はかかりますが、それが“伝統の和紙づくり”を名乗る責任だと思っています」
楮を蒸すための巨大な桶「甑(こしき)」は、明治時代から受け継がれてきたもので、直径1.4m・高さ1.6mという大きさを誇ります。この桶での蒸し作業は、今では全国でも数カ所でしか見られない貴重な光景です。この甑は、日本遺産の構成文化財にも認定されています。

▶甑で行われる「そどり(蒸す作業)」の光景
12月になると始まるこの「楮蒸し」。テレビニュース等でも「山陰に冬が来たことを告げる風物詩」として紹介され、地域の誇りとなっています。
世界に誇れる強さと美しさ
石州勝地半紙の最大の特徴は、「水に強い紙」であることです。江戸時代、商家では「大福帳」と呼ばれる顧客台帳を火事の際に井戸につけて守ったという逸話も残るほど。
一般的な和紙は、これほど水に強くはありません。当時、関西の商家の5軒に1軒が高級紙であった石州和紙を利用していたそうです。
和紙の強靭さは、繊維同士が水素結合で絡み合っていくことで生まれますが、水に浸すと結合が緩んで弱くなります。石州の和紙は、表皮と白皮の間にある微細な甘皮を敢えて残すため繊維の重なりに甘皮がこびりついて、濡れても結合が緩まない強い和紙になります。

「紙って、弱くて儚いものだと思われがちですが、実は強くて頼もしい存在なんです」
和紙と神楽、そして日本遺産へ
勝地半紙のもうひとつの大きな特徴は、石見神楽との深い結びつきです。
石見地域に伝わる神楽の中でも、桜江町は“石見神楽の源流”ともいえる文化を色濃く残す土地。その神楽で使用される幣(へい)や奉書紙にも、勝地半紙で漉いた和紙が用いられています。
2019年には「石見神楽」が日本遺産に登録された際には、勝地半紙と、甑(こしき)は構成文化財の一つとして正式に認定されました。
「和紙が神楽の“影の立役者”なんです。」

紙の“これから”のあり方
佐々木さんは、伝統を守るだけでなく、今の時代に合った紙の使い方も模索されています。「今は手紙を書かない人も多いし、障子も少なくなってきました。でもその代わりに、紙でつくるランプシェードや雑貨など、“生活に寄り添う和紙”の提案をしていきたいんです」

工房で人気の体験メニューは、はがきづくりと小さなランプ制作。草花を漉き込んだオリジナル作品は、お子様からご年配の方、そして海外のお客様にも喜ばれています。

「和紙って、光を通すと本当に綺麗なんです。優しくて、ぬくもりがあって。お仏壇のそばに置く明かりとしても人気がありますし、外国の方には“癒し”のアイテムとして受け入れられているように思います」
時代はデジタル化が進み、紙に文字を書く、ということが非日常となりつつある今だからこそ「紙」の特別感を私たちは楽しむことができると感じます。
次の世代へ、つなぐために
現在、石州勝地半紙の工房を支えているのは、佐々木さんと奥様のおふたりです。後継者不足は深刻な課題となっています。
「今はまだ、紙づくりを仕事にしたいという若者は多くありません。でも、全国で展示や発信を続けていくことで、“やってみたい”と思う人が一人でも増えてくれたら嬉しいです」
海外からの関心も高く、フランスのアーティストの方からの定期的な注文もあります。
「物語としての“和紙”をきちんと伝えることができれば、言葉が通じなくても伝わるものがあると思うんです」
和紙づくりは、単なる製造ではなく、土地の記憶を漉き込む文化の継承です。これからも、佐々木さんの手から生まれる紙が、人と人、地域と世界をやさしくつないでくれるはずです。




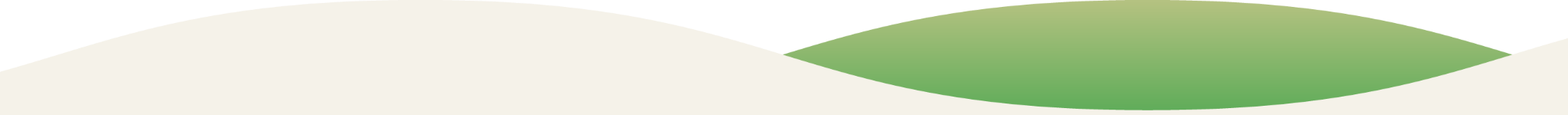



.png)
